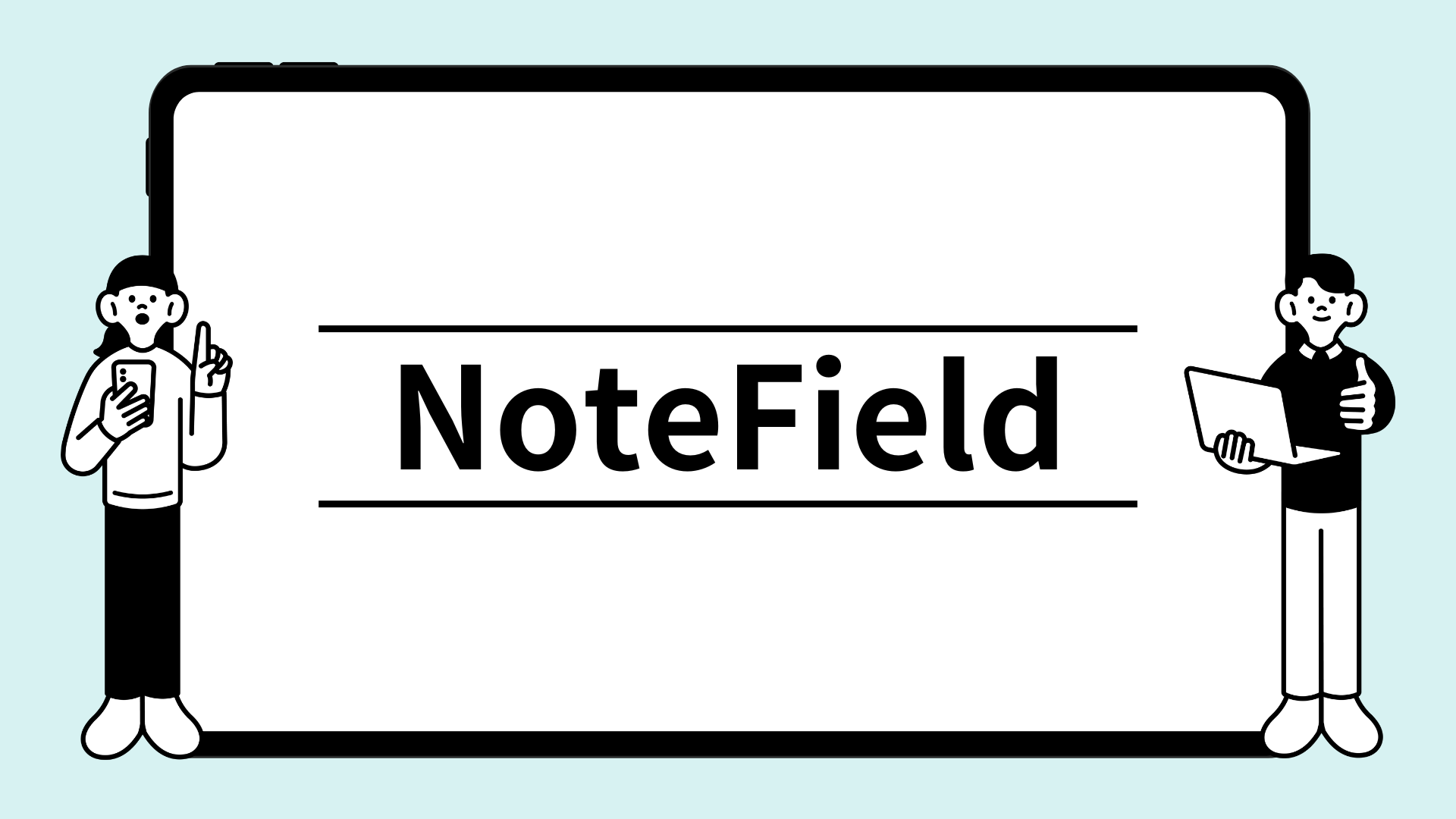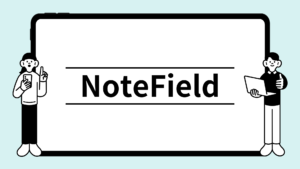AIは、ついに「こちらの意図を汲み取る」領域に到達した。
そう期待していた多くのユーザーが、ChatGPT-5を使ってある種の違和感を覚え始めています。それが、「プロンプトを守ってくれない」という問題です。
「命令通りに答えてくれない」「勝手に要約される」「丁寧に指示したのに、無視された」。
こうした声は、決して少数派ではありません。むしろChatGPT-5の“性能向上”が皮肉にもこの問題を引き起こしているとも言えるのです。
この記事では、ChatGPT-5がなぜプロンプトを無視するのか、その背景にある技術的・構造的要因をひも解きながら、「なぜこんな挙動になるのか?」「どうすれば意図通りに動かせるのか?」という視点から掘り下げていきます。
AIが「言うことを聞かない」のは進化の証なのか?
ChatGPT-5を使っていて「指示した通りに応答しない」と感じたことがある方は多いはずです。たとえば
- 「この文章を敬体で書いてください」と書いたのに、常体で返ってくる
- 「見出しはつけないで」と頼んだのに、しれっとH2タグがついてくる
- 「一切要約せず全文表示して」と伝えたのに、なぜか要約されている
これらはすべて、プロンプトに対して“意図しない最適化”が行われている典型例です。そして重要なのは、これは「誤動作」ではなく、「進化」の副作用であるという点です。
ChatGPT-5は、従来よりも高度な“意図推論”能力を備えています。つまり、ユーザーの指示よりも「文脈」や「過去の対話傾向」から、“最も自然と思われる回答”を自動で組み立てようとするのです。
この「勝手に気を利かせてくる」仕様は、雑談や曖昧な相談では確かに便利です。しかし、明示的なプロンプトに対しても同様の“先回り”が発動すると、逆にユーザーの意図から逸れてしまうことになります。
ここに、進化と暴走の境界線があるのです。
なぜChatGPT-5はプロンプトを無視するのか?技術的背景を探る
ChatGPT-5のプロンプト無視問題は、単なる「不具合」ではありません。むしろ、設計思想そのものに起因する“構造的なズレ”と見るべきでしょう。以下に、主な技術的要因をいくつか挙げます。
1. 高度な文脈予測アルゴリズム
GPT-5では、従来よりも広範囲の会話履歴と文脈をベースに、回答内容を調整する機構が導入されています。
その結果、「このプロンプトはこう解釈すべきでは?」というAI側の“意志”が入り込み、ユーザーの意図よりも“正しそうな文脈”を優先してしまうことがあります。
2. 安全性・一貫性フィルターの強化
誤情報や有害発言を防ぐため、ChatGPT-5では応答内容に対する制御がより強化されています。
しかしこのフィルターが過剰に働くと、「書いてほしいことが書かれない」「意図と異なる表現に書き換えられる」といった現象が起きやすくなります。
3. プロンプトの“最適化”をAIが勝手に行う
「プロンプトエンジニアリング」という言葉が一般化する中で、ChatGPT-5はプロンプト自体を内部で“解釈・再構成”する能力を持っています。
ところがこれが逆に、「ユーザーのプロンプト≠AIの内部処理されたプロンプト」となることで、指示が反映されない状況が発生してしまうのです。
このように、ChatGPT-5のプロンプト無視は、単なる“サボり”でも“バグ”でもなく、設計思想に由来する必然的な結果と考えるべきでしょう。
「指示を守らせるにはどうすればいいのか?」ユーザー側ができる対策
ChatGPT-5が“賢くなりすぎた”せいでプロンプトを無視するようになっている以上、こちら側にもある程度の「工夫」が求められます。ここでは、できる限り意図通りに動かしてもらうためのテクニックを紹介します。
1. 明確で具体的なプロンプトを使う
「要約しないで」「常体で書いて」など、曖昧になりがちな指示は避け、「要約禁止・全文必須」「〜です・〜ます調のみ使用」など、AIが誤解しないような“硬い表現”を意識することが大切です。
2. 制約条件を複数回に分けて明示する
長いプロンプトで一度に多くの条件を与えると、GPTは一部を取りこぼしやすくなります。可能であれば、「まず要件A」「次に要件B」と段階的に入力する方が、精度が上がります。
3. 期待される出力例を示す
ChatGPT-5は、出力スタイルの模倣が得意です。自分が望む形式での“例”を一行でも提示することで、それに倣って出力されやすくなります。これはプロンプトだけでなく、「これは見出しではなく本文です」などの補足も有効です。
4. それでも無視されたら“再プロンプト”で補正する
意図通りに動かなかった場合は、「あなたはプロンプトを無視しました。再度、以下の条件を厳守してください」と伝えて再指示するのも有効です。
GPT-5はフィードバックを踏まえて出力を変えるので、「プロンプト違反を指摘 → 再実行」という流れが功を奏します。
まとめ
ChatGPT-5がプロンプトを守らない。
この現象は、一見すると「バグ」のように見えるかもしれません。しかし実際には、AIが高度な文脈理解能力を持ったがゆえに、ユーザーの意図を「先回りして解釈する」という新たな段階に入った証拠でもあります。
私たちがAIに求めていたのは、「察してくれること」ではなく「言ったとおりにしてくれること」だったのではないでしょうか。
便利さの代償として、「言うことを聞かなくなったAI」は、ツールとしての信頼性を揺るがしかねません。
とはいえ、絶望するにはまだ早いです。プロンプトの設計を工夫し、出力例を見せ、条件を明示することで、ChatGPT-5は今でもかなり高精度に制御可能です。
扱いづらくなったのではなく、扱い方が変わったそう捉えることが、これからのAIとの付き合い方の第一歩になるのではないでしょうか。